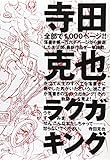普通に考えれば、才能とは少ない努力で結果を出すことのできる能力のことです。ボイストレーニングもレッスンも受けたこともないのに人並み以上に歌が歌えるならそれは才能だし、それは生まれ持った能力以外の何者でもありません。
ですが、小説に関してはまた違った考え方も存在しているようです。面白かったのがこちらの文章。
この文章の中で、小説を書く才能が3つの要素に分けて紹介されています。その3要素とは、
・欲求
小説を書いている時間が一番楽しい。また書きたいと思う。
どうしてもこれが書きたいんだ! というテーマがある。・成長
どうすれば、よりおもしろい小説が作れるか、創意工夫することに喜びを感じる。
うまく行くとさらに創意工夫を重ねたくなる。そのための労力をめんどうだと思わない。・実績
長編小説を何作品も書き上げている。
というもので、中でも最初の「欲求」が最も大事なのだ、と指摘されています。
これは普通に考える「才能」とは異なります。どんな能力でも「一万時間の法則」があって能力を開花させるには時間をかけて磨かないといけないわけですが、強制でもされない限り、何かを1万時間も続けるのは、それがよほど好きでなければ不可能です。だから「欲求」が最も重要、ということなのでしょう。
本来の意味での「才能」がある人は同じ時間をかけても上達が早いでしょうが、そういう「才能」が欠けていたとしても時間をかければ能力は向上し得るわけで、やはり「欲求」が重要だとなります。欲求がなければ成長も感じられず、実績も積めないですから。何かに没頭できるほどそのことが好きであるなら、それは生まれつき才能を持っているのと同じことなのかもしれません。
これは小説以外の分野でも言えることだと思います。絵師の人などを見ると暇さえあれば落書きしている人というのは多いようですし、気が付けばやってしまうことだからこそ技術が向上するようです。寺田克也もそんな人だったようです。
じゃあ、下手の横好きってなんなのか。意欲があるのに下手な人だっているんじゃないの?という疑問が当然出てくるわけですが、このことについても同サイトに回答がありました。
つまり、好きだけど下手だというのは、「好きのレベルが低い」ということなんですね。私はシヴィライゼーションというゲームが好きですが、せいぜい貴族レベルで勝てればいいか、という程度の「欲求」しかないので、全然上達しません。天帝レベルで勝ちたい人なら上手い人の動画も一生懸命研究するだろうし、日々攻略法の開発に余念がないでしょう。生まれつきの「才能」が同程度であっても、そういう人と私とでは「欲求」のレベルが違いすぎるので、差がついてしまうのは当然というわけです。
こう書いてくると、やはり努力が大事なのだ、というごく当たり前の結論になりそうですが、それはちょっと違います。 才能の2番目の「成長」について「どうすれば、よりおもしろい小説が作れるか、創意工夫することに喜びを感じる」と書かれていますが、これは書く事を楽しめるかどうか、ということです。楽しんでやっていることならそれは努力ではありません。孔子の言葉を借りるなら、
孔子の言葉ですが、”これを知る者はこれを好む者に如かず、これを好む者はこれを楽しむ者に如かず”というものがあります。楽しむ事が個人としては最上の戦略であるとおっしゃっているように思います。努力は夢中に勝てないんです。
— 為末 大 (@daijapan) 2014, 2月 21
ということです。楽しんでいる人には誰も勝てません。
……とここまで書いてきて思ったのは、「いや、その欲求が強いだとか、成長を楽しめるだとかいう能力だって先天的なものじゃないの?」ということなんですが、そこまでは私にもわかりません。「欲求」は能力が伸びるに従って強くなりそうだし、「成長」に関しては工夫次第では楽しめそう、といった感じでしょうか。ここまで先天的だと本当に何もかも生まれつきということになってしまうので、ここはもう少し希望を残すような解釈をしておきたいところです。