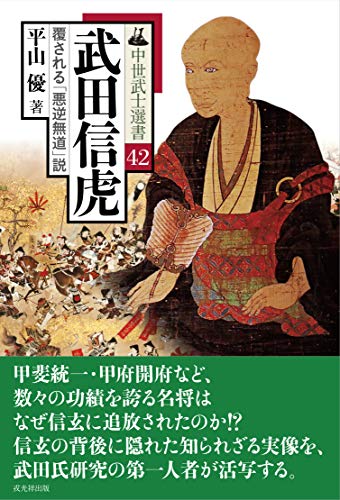古代中国史の入門書として文句なしにおすすめできる本が出た。本書『戦争の中国古代史』はタイトル通り軍事についての記述が多いものの、殷~前漢の政治史を要領よくまとめているので古代中国史の概説書としても使える一冊になっている。古代中国史の最新知見を盛り込みつつ、殷の女性兵士や武霊王の「胡服騎射」改革の真の目的、「宋襄の仁」が当時の「軍礼」に基づく行為だったことなど、興味深いトピックを数多くとりあげているので、中国史に少しでも関心のある人なら楽しく読みすすめられる内容になっている。
以下、興味を引かれた内容についていくつか紹介する。
殷に「女性兵士」は存在したか
殷の王妃・婦好は「戦う王妃」として有名だ。実際に彼女と軍事とのかかわりを示す甲骨文が出土している。だがこの本によれば、殷代には女性の司令官だけでなく、女性兵士が存在した可能性があるという。前掌大遺跡や少陵原遺跡など、下層の貴族や平民の女性の墓にも武器が副葬されている例があるからだ。女性と思われる人物とともに埋葬されている玉戈には被葬者の軍功らしき文章が書かれているものもあり、この点からも女性が出征していた可能性が指摘されている。
武器の副葬は魔除けの可能性もあり、必ずしも女性の出征を示す証拠にならないという批判も出ているが、これらの出土品は古代の戦争の実態を知るうえで貴重な史料であることは間違いない。今まであまり殷代の歴史に興味がなかったが、この話題だけでも殷代の出土品が魅力的であることがわかった。
「宋襄の仁」は当時の戦争のルールに基づく行為だった
「宋襄の仁」という有名な故事がある。宋の襄公が川を渡る途中の楚軍を攻めず、陣をととのえるのを待ってから戦って大敗したため、「無用の情けをかける」意味でよく用いられる。ここだけを見ると襄公はいかにも地に足のつかない理想主義者にしかみえない。だがこの本によれば、渡河する途中の敵を攻めないのは当時の「軍礼」(戦争のルール)にもとづいた行為で、襄公はこの規範に従っていたのだという。
軍礼とは「スポーツで言えば競技のルールであるとかスポーツマンシップのようなもの」とこの本では説明される。この軍礼においては渡河の途中の敵を攻めてはいけないことになっていたようで、楚もこのルールを共有している。
高木氏は、『佐伝』の中の戦争に関する記述を参照すると、当時の人々が、弓矢による攻撃を交互に行うというルールや、窮地にある敵、脆弱な敵、負傷して戦意のない敵、喪中の敵などへの攻撃を控えたり、敵であっても武勇に優れた者には敬意を払うといった規範意識を共有していたことが見いだせるという。襄公の場合は、川を渡る最中で窮地にある敵を攻撃しないという規範を実行したことになる。
実際に敵軍が川を渡っている時に攻撃をしてはいけないというルールが共有されていたようで、『佐伝』僖公三十三年には、晋と楚が汀水という川を挟んで対峙した際に、晋軍が楚軍に「そちらが川を渡るのであれば、わが軍は後方に退くので、その間に川を渡って陣を整えよ。あるいはそれが嫌ならそちらが退いて我が軍が川を渡るのを待て」と提案し、楚軍は自分たちが後方に退いたという話が見える。泓の戦いで宋を破った楚も、ここでは渡河の軍礼を共有していたということになる。(p128)
ルールにのっとって正々堂々と戦うべき、という規範が、春秋時代にはまだ存在していた。この規範はしだいに崩れていき、やがて孫子が「兵は詭道なり」と主張するように不意打ちや騙し討ちなどを戦争の本質とみなす兵家が台頭してくる。『孫子』の成立は春秋時代後期と考えられているが、それが本当なら戦国時代に入る前からすでに戦争観は現実的で厳しいものになっていたことになる。
「胡服騎射」改革と趙・燕・秦の「小帝国」化
戦国時代の軍事改革として有名なものに、趙の武霊王の「胡服騎射」がある。これはよく知られているとおり、騎兵を導入することで軍事力の強化をはかったものだ。だがこの本では「胡服騎射」はたんなる軍制改革ではなく、林胡や楼煩などの遊牧民との親和をはかる礼制・外交改革でもあったという見方を紹介している。武霊王は趙を中原の国家としてだけでなく、「胡人」の政権としても位置づけようとしていたというのである。これは趙の「帝国化」へ向けた動きであり、事実武霊王は北方の遊牧民の制圧に成功している。
この「帝国化」の動きが趙だけでなく、他国でも進行していたことがこの本では指摘されている。たとえば燕は遊牧民の東胡を攻め遼東や鴨緑江の東へと勢力を広げているし、秦もまた義渠や巴・蜀を滅亡させ支配下に置いている。三国とも支配領域を「中華」世界の外にまで押し広げていて、「小帝国」を形成している。こうした動きはやがて秦が中国を統一することで生まれる大帝国への胎動と位置付けられる。楚も「帝国化」をめざしていたと本書では指摘されるが、楚は秦の名将・白起に首都を攻め落とされたため強国の地位から脱落した。すでに「帝国化」していた趙も長平の戦いで秦に大敗したため、これ以降は秦一強の時代になる。「小帝国」同士の争いを制した秦が中国を統一するのは、歴史の必然だった。
兵馬俑の髪はなぜ右側で結われているのか?
秦の兵馬俑はあまりにも有名だが、もの言わぬ兵馬俑も資料としてはかなり雄弁で、秦について多くを語ってくれる。この本では兵馬俑の髪型に注目している。秦の兵士は髪を右側に束ねて結っているが、これを結髪とよぶ。なぜこの髪型なのだろうか。この本で紹介する鶴間和幸氏の見解では、結髪にすると髪が砂と埃から守られるのだという。つまり、兵馬俑の兵士の髪型は、首都咸陽付近の防衛か、胡人との戦いを意識したものということになる。趙や燕などの「小帝国」を併呑し大帝国となった秦は、必然的に匈奴などの胡人と向き合わねばならないことになる。結髪は秦を象徴する髪型といえるのかもしれない。
さらには、秦では髪型は軍隊編成上の身分標識でもあったという。冠をかぶらず髪をあらわにしているのが当時の一般兵士の髪型だったようだ。兵馬俑の結髪は実用的だっただけでなく、その地位を表すものでもあった。あまり史料には登場しない一般兵士のことを知る手がかりとして、兵馬俑がきわめて重要であることを再認識させられる。
殷周史の入門書としても便利
以上、面白かった個所をいくつか紹介したが、著者の佐藤信弥氏は殷周史の専門家であるだけに、この本はマイナーになりがちな西周時代についての記述も充実している。周が牧野の戦いで殷に勝利した要因として戦車戦に習熟していたことがあげられること、周の外敵だった獫允(犬戎)は戦車を所有していて周と同じ文明圏にあったらしいことなど、この時代にもとりあげたかったトピックが数多くある。西周時代には一章が割かれているので、ぜひ読んでこの時代についても知ってほしい。西周時代の馬車はイラスト付きで解説されているので、当時の戦車戦を想像する手がかりにもなる。西周に興味がわいたら同氏の『周―理想化された古代王朝』を読めば、さらにこの時代をくわしく知ることができる。